腸管出血性大腸菌(O157、O111等)の知識
ページ番号:559955186
更新日:2025年3月24日
腸管出血性大腸菌について
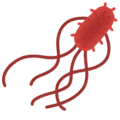
腸管出血性大腸菌は牛等の腸管などにいる菌で、ベロ毒素と呼ばれる毒素を作り、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)(注釈1)を起こします。代表的な血清型は「O157」で、その他に「O26」や「O111」が知られています。 子ども、とくに乳幼児の場合は、重症になりやすいので注意が必要です。
(注釈1)HUSとは、ベロ毒素により血球や腎臓の尿細管細胞が破壊されたりすることで、急性腎不全や尿毒症、溶血性貧血、血小板減少などを起こす状態。
症状
主な症状は、下痢、腹痛です。鮮血便がみられることがあります。
症状のある者の数パーセントに、溶血性尿毒症症侯群(HUS)を併発することがあります。腹痛、下痢、血便がある場合は、早めに受診することがとても大切です。
潜伏期間
平均4日から8日
原因食品・感染源
食品から
- 生肉(レバ刺、ユッケ)、半生・加熱不十分な食肉を食べた時
- 食肉等から二次汚染した食品を食べた時
- 野菜とその加工品
- 飲用水
人や動物から
- 感染している人からの二次感染
- 子ども用ビニールプール
- トイレ、オムツ、お風呂等を介した感染
- 動物への接触
腸管出血性大腸菌は、微量の菌により感染が成立します。そのため、人から人への感染が起こりやすく、保育園や幼稚園での集団発生がときどき見られます。
予防方法
子どもや高齢者が肉を生で食べると、特に危険です
- 生食用食肉(牛の肉であって生食用のものに限る:ユッケ、タタキ等の牛肉)について規格基準があります。
- 牛生レバーの提供が禁止されています。
規格基準に適合した生食用食肉であっても、腸管出血性大腸菌などの食中毒を完全に除去することは困難なことから、食中毒の危険性は「0(ゼロ)」ではありません。子どもや高齢者等の食中毒に対する抵抗力の弱い方は、肉を生で食べるのは控えましょう。
家庭での予防方法
- 肉専用のまな板・包丁を用意して、肉類とサラダやフルーツなどの生で食べるものは、別々に調理しましょう。
- 生肉を触った後は、しっかり手を洗いましょう。
- 肉を焼く箸と、食べる箸は別々にしましょう。バーベキューや焼肉をする時は、肉の中までしっかり加熱しましょう。
食中毒予防の3原則については こちら を参照してください
かかってしまったら(家庭や施設での二次感染予防)
- 最も重要な予防方法は、手洗いです。調理や食事の前、用便後、帰宅時は、流水・石けんを使って手を洗う習慣を持ちましょう。
- オムツ処理や排便介助した後は、その都度必ず、流水・石けんで手を洗いましょう。手洗いは、洗面台で行い、台所ではしないようにしましょう。ゴム手袋や使い捨ての手袋等を使用するのも効果的です。
- 下痢などの症状がある時は、早めの受診とともに、登園や出勤を控えて自宅で休養しましょう。
- 日々のお子様の様子を観察し、体調変化について保育園や幼稚園の先生と連絡しあいましょう。
- 下痢症状がある時は、プールは控えましょう。
- 患者の便で汚れた下着は、薬品等の消毒(つけおき)をしてから、家族のものとは別に洗濯しましょう。
- 患者はできるだけ浴槽につからず、シャワー又はかけ湯を使うようにしましょう。また、浴槽に入る場合は、最後に入浴し、家族と一緒に入らないようにしましょう。タオルはひとりで一枚を使用し、共用しないようにしましょう。
- 水洗トイレの取っ手やドアのノブなどよく触る場所や、子どもがなめたおもちゃは、消毒用アルコールなどを使って消毒しましょう。消毒するときは、ガーゼやティッシュにアルコールを含ませて拭き取り、噴霧はやめましょう。


腸管出血性大腸菌に関する情報
![]() 食品衛生の窓「腸管出血性大腸菌O157」(東京都ホームページ)
食品衛生の窓「腸管出血性大腸菌O157」(東京都ホームページ)
お問い合わせ
食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0691
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ




